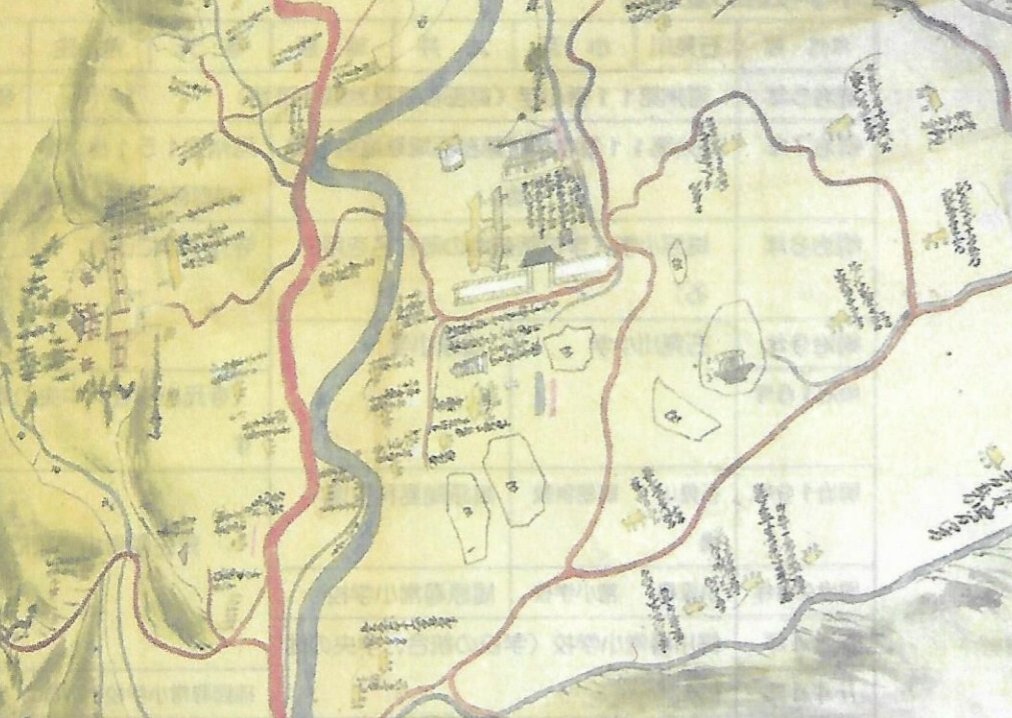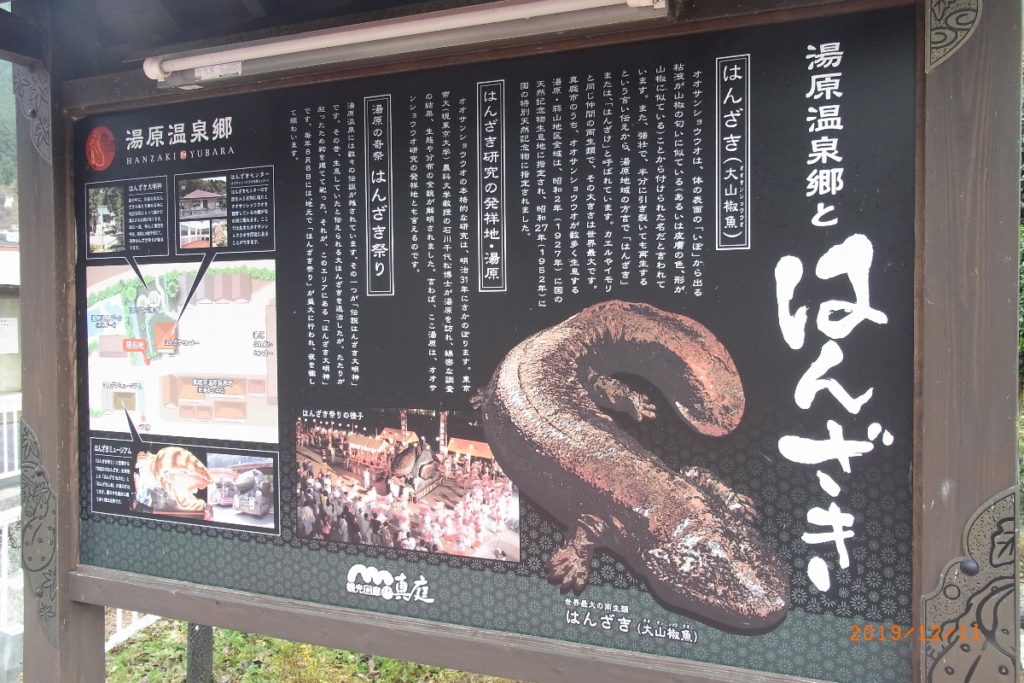ぶらりと出た旅先で時々、おもしろい里伝説に出会います。大阪奥河内の三方山に囲まれた山深い麓に古刹岩湧寺がひっそり佇みます。熊野から吉野まで険しい大峰奥駈修行が有名ですが、大阪・和歌山県境に連なる和泉山脈から奈良・大阪県境の金剛山脈連なる峰々に「葛城二十八宿経塚」があります。修験道聖地の岩湧山は元山上(山上ヶ岳)と呼ばれて、山深い岩湧の森の山斜面に沿う洞窟に龍が閉じ込められた伝説が残ります。
龍伝説とは
岩湧寺参道に立つ標識 臥龍洞

岩の涌き出ることから名づけられた涌出山・岩湧寺は、岩湧山裾野に佇む山深い古刹です。境内に佇む三門二層の多宝塔辺り急山斜面に洞窟があります。昔々この洞窟に住む龍が村の田畑を荒らし、困り果てた村人が岩湧寺の僧侶に頼み法力をもって龍を退散させた伝説が残っています。
龍を閉じ込めた洞窟
臥龍洞は巨岩に挟まれた洞窟

山深い辺は中世時代に大峯奥駆と並んで栄えた葛城二十八宿がある、葛城修験の道場あった地域です。龍を退治した僧侶は修験道の開祖・役小角とも伝えられ、雨乞いの神様として信仰される龍神さまと結びついた伝説とも伝えられます。岩湧寺から下ってある滝畑には、むかし湖があって龍(龍神)が住んでいたようです。
水不足に苦しむ河内と和泉の村人が湖水を取り合ったため、河内の神と和泉の神が競争し滝畑に先着した方に水を流すことになり、結果は河内の竜神が勝ちました。龍は約束通り水を河内に流したという竜神伝説も残ります。
祀られる修験道の第十五経塚

岩湧寺から滝畑に向かう峠付近にある第十五経塚の石塔は、七大龍王と金剛童子が刻まれています。石積みや五輪塔、祠など多様な経塚は山尾根から麓の郷まで行場が広がります。役行者が法華経二十八品を一品ずつ埋納した経塚は、葛城修験の修行道「葛城二十八宿」と呼ばれ和泉山脈・金剛山地にまたがります。
絶壁の岩肌沿いに社
白成大神祀る巨岩に囲まれた神域

鬱蒼とした森深い谷間にある滝は、水量少なく滴る程度に山肌に流れています。ロッククライミングができるような垂直に立ちあがる岩壁に思わず唖然、人の気配も無く岩窟に囲まれ森閑としたスピリチュアルな雰囲気が漂います。
岩壁を背に神秘的な社が佇み、白成大神を祭るお稲荷さん守るようにコンコン様がおわします。山肌に僅かながら流れる千手滝と不動滝は、その昔に龍の力が封印されたのか勢いがありません。
絶壁に祀られる行者堂

岩湧寺境内から登る兼松新道は途中に水飲み場があり、尾根頂きの五ノ辻と合流しから尾根伝いに岩湧山頂へと通じています。 境内から山裾の急坂木階段を上がった所に、左側の岩場を入ると行者堂が祀られています。
祠中に飯縄権現像と役小角像が安置される行者堂の周りは、垂直に落ちる崖で大変危険です。白成大神を祀る岩峰の上に祀る行者堂の岩崖下には行者滝が落下しています。 一人で立ち入らないようにしましょう。
岩湧の森とは
岩湧寺境内に咲く秋海棠

文武天皇の勅願寺で大宝年間に修験道の開祖・役小角が開基した山腹岩湧の森にある岩湧寺は、多宝塔の本尊・大日如来が平安末期の作で重要文化財に指定されています。古くは天台宗寺院でしたが、明治に入り融通念仏宗に転じ河内長野市古野の極楽寺の末寺です。9月中旬には境内いたる所が秋海棠の花で覆われて、この時期の岩湧の森は秋海棠の花が咲く壮観な森の園になって多くのハイカーが訪れます。
岩湧寺境内の雨乞い地蔵菩薩

岩湧寺境内から行者の滝を過ぎ渓谷沿い道を下り降りると雨乞い地蔵があります。雨乞い地蔵菩薩の岩湧山から湧き出る岩清水は、言伝えでは日照りで村人が飲み水に困り雨乞いした時に天狗が現れ錫杖で一突きでこんこんと水が湧き出たとの伝説があります。長寿水と伝わるこの湧水は南海高野線・天見駅前にある店等で料理にも利用されていると聞かれます。
臥龍洞へのアクセス
レンタル自転車での行き方

最寄りは南海高野線・近鉄長野線の河内長野駅で下車します。臥龍洞は岩湧の森・境内近くで、岩湧寺がある山深い岩湧の森まではバス便も少なく、バス停留場(神納)からも歩くのに距離があるのでレンタル自転車が便利です。
駅前バスロータリーの7番バス停留場の前にある観光案内所でレンタル電動自転車を利用し、駅前案内所から岩湧の森まで20kmほどを電動自転車で約90分を目安に走ります。