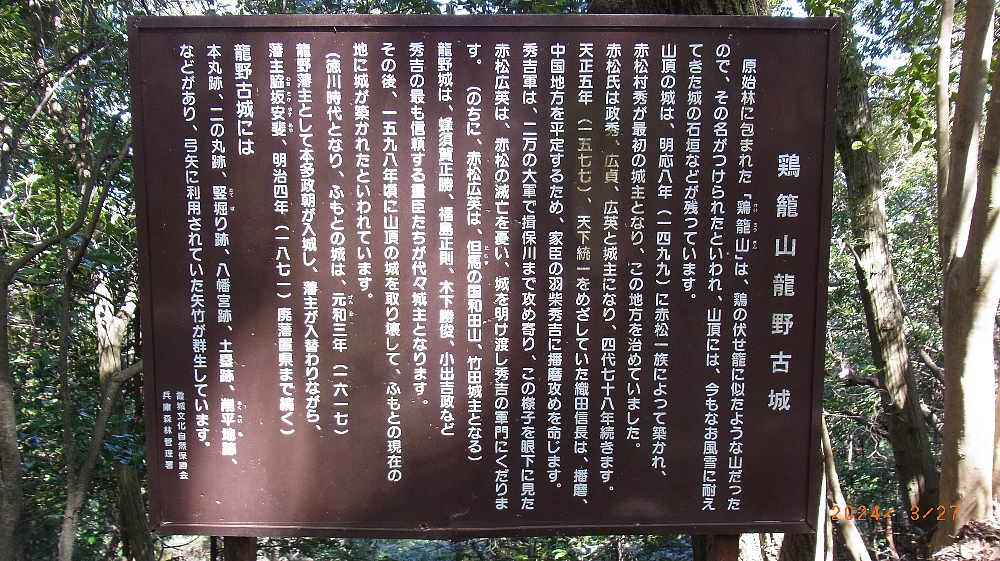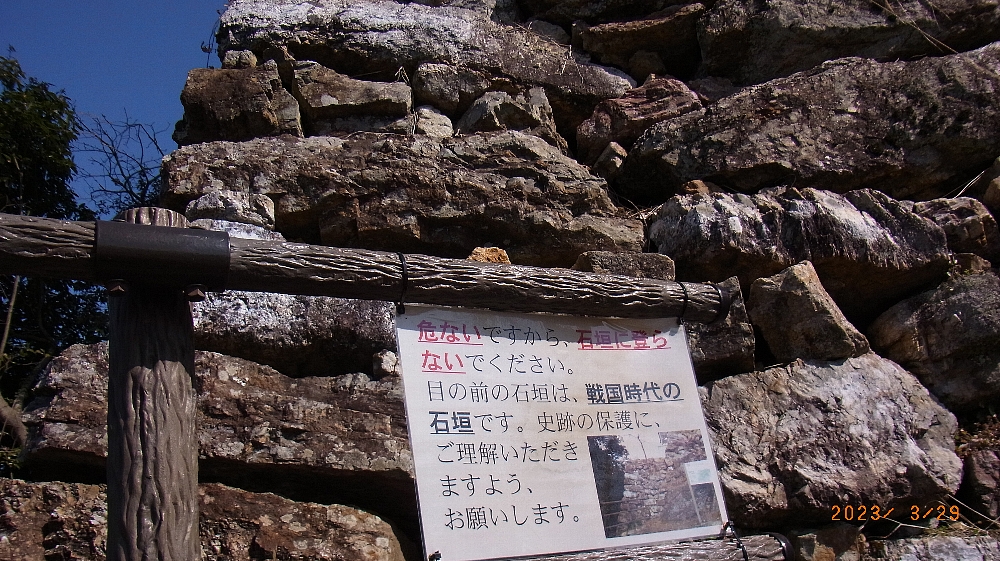日本一の石垣で有名な名城とも言われる丸亀城は、現存十二天守の中で一番小さな天守を持つ日本百名城にも選ばれています。「扇の勾配」と呼ばれる石垣が山麓から山頂まで4重に重ねられ、総高60mの規模で、三の丸石垣だけでも一番高い部分が22mあるようです。現存天守でもっとも小規模ながら、本丸にある御三階櫓は丸亀城は1615年の「一国一城令」により破却の危機にさらされますが、当時の藩主である生駒正俊が要所要所を樹木で覆い隠して立ち入りを制限し、城を破却から守ったと伝わります。後に山崎氏、京極氏が入封し、城の修築を行われます。現在の天守(御三階櫓)や石垣は京極氏の時代に完成されたようです。
お堀からの丸亀城

標高約66mの亀山に築かれた平山城で、別名亀山城と呼ばれています。本丸・二の丸・三の丸・帯曲輪・山下曲輪があり、東西約540m・南北約460mのうち内堀内の204,756平方メートルが史跡範囲です。「石の城」と形容される丸亀城は石垣の名城として全国的に有名です。大手門から見上げる夕暮れの天守はちんまいながらも威厳にがあり、心が和みます。400年の時を経た今日でも決して色あせることなく、自然と調和した独自の様式美をはっきり現在に残しています。(公財)日本城郭協会が選定した「日本100名城」にも選ばれ、花見や散歩など市民の憩いの場として親しまれています。
本丸の現存木造天守

山上の最高所が本丸です。本丸には、天守のほかに隅櫓・渡櫓・土塀が石垣上に巡っていました。礎石、排水路も一部復元しています。高さが約15m程あり、三重三階の造りで、全国に12しか残っていない木造天守の1つです。四国に残る木造天守の中で、最も古い1660年に完成しました。唐破風や千鳥破風を巧みに配置し、北側には石落しや素木の格子を付け、意匠を凝らしています。天守の入場は有料(’24年時は大人200円)です。 讃岐富士を正面に見れる月見櫓からは風光明媚な景観が楽しめます。
本丸西側の石垣

見返り坂を登りきると二の丸と三の丸に、三の丸南側・搦手口は山崎時代の大手とか、ハバキ石垣はサヤ石垣とも呼ばれる石垣が見どころです。石垣が膨らんだ箇所が崩れないように外側から押さえて保護する役割があるようです。
ハバキ石垣も山崎氏時代に築かれたようで、建物が建っているので石垣を解体修理をせず、ハバキ石垣を築き石垣保護をされたと思います。石垣が有名な丸亀城は「石垣の名城」と言われ、城郭石垣を築く技術が最高水準?江戸時代初期に作られ、優れた技術の石垣を見ることができます。特に丸亀城の主要な石垣は、高くて美しい曲線が特長です。
高石垣と算木積

丸亀城三の丸は高石垣で築かれ北側の石垣は、丸亀城の石垣の中で最も高く、20m以上の城壁が続きます。隅角部の石垣は算木積みされた美しい曲線美で、「扇の勾配」と呼ばれています。
石垣の隅角部(出隅)の石垣は算木積みと呼ばれる積み方です。角石は長方体の石を用い、長い面を大面、短い面を小面といい、大面と小面を交互に組み合わせ小面の角石の横には角脇石を配することで、より強固な積み方となり、美しい勾配の高石垣を築けるようになったようです。
大手二の門

一の門と同時に建てられた、高麗門形式の門です。大手とはお城の正面のことを指し、追手とも言われるようです。大手二の門は丸亀城の顔にふさわしく、石垣に使用される石は大きく、ノミの跡も美しく仕上げられています。大手枡形は城の正面玄関であり、鏡石と呼ばれる2mを超える大きな石が用いられています。鏡石は大手枡形などの城の重要な箇所に魅せる石垣として用いられたようです。
江戸時代からの現存建物の太鼓門とも呼ばれた大手一ノ門は、大手二ノ門、天守と共に国の重要文化財に指定です。大手一ノ門は内部が無料公開されていて、備え付けの布草履に履き替えて見学が可能、攻め寄せる敵を撃退する「石落とし」や、鯱なども展示されてました。
玄関先御門から見る天守

京極氏屋敷の表門にあたる旧藩主居館だった玄関先御門は、「御殿表門」とも呼ばれ、江戸時代初期に建てられました。お城の門としては珍しい薬医門形式で、屋根越しに見える天守との調和も素晴らしい。高々と積まれた石垣日本一高い丸亀城は、お堀から天守まで、総高60mにも及ぶようです。その石垣の上に、日本一小さな天守がちんまりと乗っている感じです。
アクセス

四国に渡り、電車の利用ですと予讃線のJR丸亀駅から徒歩15分ほどで丸亀城跡の城門に到着します。城跡辺りにはコンビニやお好み焼屋さんも、30分程歩けばうどん屋も有って飲食物には困らないと思います。丸亀城跡に来られる方は、他の観光地にも寄られる方が多いです。高松城(JR高松駅下車)や金比羅さん(JR金刀比羅駅下車)へのアクセスも電車ですと丸亀を拠点にすれば便利だと思います。